JR東日本の「Suica」が大きな話題になっている。ひとつは長く愛されてきたSuicaペンギンが2026年度末をもって終了すること。
そしてもう一つがSuicaのバーコード化である。QRコードアプリが用意され、既存のICカードと残高を共有しながら決済方法が選択可能になる。

同社は磁気切符も廃止予定。各駅の人員削減を進めながら効率よく乗車してもらう対策とも言えるだろう。
しかし話はそう単純ではなさそうだ。何故「Suica」はバーコードを搭載するのか。背景を探りながらメリット・デメリットを筆者の視点から考察したい。
何故QRコードを搭載するのか
結論から書くと「Suica」のバーコード搭載は時代の変化に抗うものだろう。同サービス開始の2001年当初、日本はまだまだ現金社会だった。
おサイフケータイなど無いし、クレジットカードも今ほど一般的ではない。現金をチャージして持ち歩ける「Suica」は当時のキャッシュレスとしては民主的かつ革命的だったのである。

そして人々もコンビニや駅のキオスクでちょっとした買い物をする程度。あとは基本的に乗車券として使うから、それ以上の機能はあまり求められなかった。
この状況が一変したのはコロナ禍だ。安倍前政権のキャッシュレス推進施策でPayPayをはじめとするQRコードが一気に普及。
またクレジットカードがタッチ決済に対応すると人々はコンビニやスーパーどころか、ちょっとお茶するだけでもキャッシュレス決済を使うようになった。そしてこの頃から「Suica」に弱点が目立つようになる。

「あれ?Suicaに毎回チャージするの面倒じゃない?しかも何買ったか履歴がわからないし、2万円までしかチャージできない。」と。
オートチャージ対応の「VIEWカード」もコンビニやスーパーではこの機能が使えない。つまり乗車券としての立場は揺るがないものの、強いキャッシュレス規格になれないことに気がついた。
また押し寄せるインバウンド顧客と半導体不足によるSuicaカード販売停止。これが渋々バーコード搭載に至った背景ではないだろうか。
メリット
ではQRコード搭載で何が起こるのか。大きいところでは決済上限30万円の引き上げだろう。電車に乗らないときでも「Suica」アプリで大きな買い物ができるようになる。
例えば「PayPayポイントもJREポイントも好き」という方は決済手段を一元化して効率よくJREポイントを貯められるはず。
また2026年秋には送金機能も実装予定。小さなお子さまがいる家庭ではお小遣いを、大人の集まりでは飲み会の割り勘に使うといったことも可能になる。
よく分からない新興サービスではないこと。お年寄りから若者まで広く知れ渡った「Suica」という安心感は一定の需要を生み出すだろう。
あとは繰り返すがFeliaのないスマートフォンでも電車に乗れることもメリット。ただしガジェットが好きな当ブログの読者以外にはほとんど響かないかもしれない。
デメリット:後払いは民主化されるのか
まだ詳しい情報が出揃っていないため、正直なところデメリットは見当たらない。しかし心配な文言が飛び交っている。
日本経済新聞によると「ビューカードとひも付ければ、後払い方式を選択することもできる」という。
できればここは真っ先に解決して欲しかった。上限30万円の引き上げは素晴らしい対応だと思うが、弱点とされる都度チャージが解決されなければ、使い勝手は根本から覆せないのではないだろうか。
また引き続きICカードの上限は2万円。臨機応変にバーコードを使い分けるか、いっそのことQRコードに乗り換える必要が出てくる。しかしバーコードを取れば処理速度のメリットは失われる。
同社の動きは競合から5年、6年と遅れているのも事実。欲を言えばあと1つ、2つライバルをあっと言わせる決定打が欲しいところである。
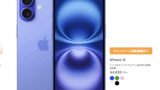
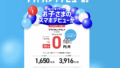

コメント